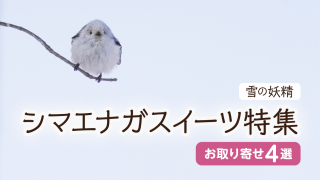北海道産長いも完全ガイド:旬・栄養・品種別特徴とおすすめレシピ

長いもってそもそも何?

「長いもって、そもそもどんな野菜なの?」
そんな疑問を持つ方も少なくないと思います。
北海道出身の方にとっては、とろろご飯やお好み焼きに入れる食材として“当たり前”の存在かもしれません。しかし、地域によっては長いもがあまり身近ではなく、「山芋は知っているけど長いもは食べたことがない」という方も少なくありません。実際、関東・東北・北海道などで多く流通していますが、西日本では自然薯や大和芋の方が馴染みがあるという声もあります。
長いもは山芋の仲間のひとつで、細長い形をしており、皮は薄くて調理しやすいのが特徴です。すりおろせば“とろろ”としてなめらかな食感に、短冊切りにすればシャキシャキした歯ごたえに変わる、とても万能な野菜なんです。
自然薯や大和芋と比べると粘りは少し弱めですが、その分クセが少なく、どんな料理にも合わせやすいのが魅力。淡白な味わいで、家庭料理から料亭の一品まで幅広く使われています。
栄養面でも優秀で、消化を助ける酵素「ジアスターゼ」、疲労回復に役立つ「アルギニン」、むくみ予防に効果的な「カリウム」、腸を整える「食物繊維」などが豊富。まさに“健康野菜”と呼ぶにふさわしい存在です。
旬は秋から冬にかけて。北海道の厳しい寒暖差が育てた長いもは、粘りと甘みがしっかりしていて、まさに今食べたいごちそう野菜なのです。
北海道は日本一の長いも産地
ご存知でしたか? 実は長いもの都道府県別生産量、北海道が全国第1位。
特に十勝地方の大正地区やオホーツク・網走地域が有名で、近年は台湾など海外への輸出も伸びています。
北海道の長いもは、畑の土を深く柔らかく耕し、1本1本丁寧に支柱を立てながら育てられます。収穫は折れやすいため、手作業で少しずつ掘り出す繊細な作業。輸送時には折れ防止のためにおが屑で包むほど、大切に扱われています。
主な産地とその特徴

・十勝地方(大正地区・池田町など)
北海道を代表する一大産地。形が整い、贈答用としても人気。「大正長いも」はブランド品として知られています。

・オホーツク地方(網走市・大空町など)
オホーツクの冷涼な気候で育ち、甘みと粘りのバランスが抜群。輸出用にも選ばれる品質です。
・上川地方(旭川周辺)
内陸の気候を生かして栽培され、粘りのしっかりした長いもが育ちます。安定した出荷量も魅力です。
こうした地域ごとの個性が、北海道産長いもの奥深さをつくっています。
長いもの旬と掘り方の違い

長いもは一年中スーパーに並びますが、実は旬があります。
・秋掘り(10〜12月):掘りたてのみずみずしさとシャキシャキ感が抜群。生で食べると格別です。
・春掘り(3〜4月):地中で一冬寝かせてから掘るため、水分が落ち着き、粘りと甘みが増します。煮物やすりおろしにすると濃厚な味わいに。
市場には貯蔵された長いもが一年中出回っていますが、やはり旬の秋掘り・春掘りは別格。食べ比べると「これが旬の味か」と違いがわかります。
長いもの栄養と健康効果

長いもは「体に優しい食材」として昔から重宝されてきました。その理由は豊富な栄養にあります。
・ジアスターゼ:でんぷんを分解し、胃腸の消化を助ける
・アルギニン:疲労回復・免疫力アップに効果的
・カリウム:体内の余分な塩分を排出し、高血圧予防に役立つ
・食物繊維:腸内環境を整え、便秘解消をサポート
さらに古くから漢方薬や薬膳料理に使われ、「滋養強壮に効く食材」としても知られています。
北海道で人気の長いも3品種とおすすめの食べ方
ここからは、食べレア北海道で買える代表的な3品種をご紹介します。
ネバリスター(5.0kg)
長いもの軽やかさと、大和芋の強い粘りを掛け合わせた新品種。
・特徴:とろろにした時の強い粘りと甘み
・おすすめ:とろろご飯、山かけそば、麦とろ、お好み焼き
・こんな方に:粘りをしっかり味わいたい方

大正長いも(2Lサイズ 10kg)
十勝・大正地区を代表するブランド長いも。見た目も美しくギフトにもぴったり。
・特徴:みずみずしく、クセがなく食べやすい
・おすすめ:短冊切り、バターソテー、煮物
・こんな方に:ご家庭用はもちろん贈答品にも最適

網走産 長いも(3kg)
オホーツクの寒冷な気候で育つ長いも。甘みと粘りのバランスが魅力。
・特徴:ほのかな甘みとほどよい粘り
・おすすめ:酢の物、サラダ、軽い炒め物、アヒージョ、お好み焼き
・こんな方に:日常の料理に幅広く使いたい方

調理のコツと保存方法
・おろし方で食感が変わる
鋭い刃でゆっくりすればなめらか、粗めにおろした後すり鉢で仕上げればふわふわ食感に。
・皮ごと食べるのがおすすめ
栄養は皮の近くに多いため、タワシでこすってそのまま調理すると良い。
・保存のコツ
丸ごとなら新聞紙で包み冷暗所に。カット後はラップに包み冷蔵庫へ。すりおろしてチャック付きポリ袋に入れて冷凍保存するのも便利です。冷凍しても栄養価は変わりません。
栄養価を高める食べ方と調理例

長いもは調理法によって栄養の引き出し方が変わります。
1.生で食べる:酵素をそのまま摂れる(とろろ、短冊)
2.皮ごと調理:ポリフェノールやミネラルを逃さない(素揚げ、ステーキ)
3.酢やレモンと一緒に:ビタミンCの酸化を防ぎ吸収率UP(酢の物、サラダ)
4.発酵食品と合わせる:腸活&免疫サポートに(納豆とろろ、味噌とろろ汁)
5.加熱で甘みを楽しむ:でんぷんが糖化してホクホク感に(バターソテー、煮物)
一度は試したい!長いもレシピ

・味噌とろろご飯:とろろに味噌を加えてご飯にのせ、ネギと海苔をトッピング。
・長いもステーキ:輪切りにしてバターで焼けばホクホク。青のりをまぶせば磯の香りも相まってお酒のつまみにも◎
・長いも揚げスティック:皮ごと揚げれば香ばしく、おつまみに最適。
よくある質問(FAQ)

Q. 長いもと山芋の違いは?
A. 山芋は総称で、自然薯・大和芋・長いもなどが含まれます。長いもはクセが少なく万能に使えるのが特徴です。
Q. 長いもは生で食べても大丈夫?
A. はい、生で食べられる珍しい芋です。とろろや短冊切りがおすすめです。
Q. 長いもは加熱すると栄養価は失われますか?
A. 長いもに含まれる消化酵素「ジアスターゼ」などの一部の酵素は熱に弱いため、加熱すると働きが弱まります。そのため「とろろ」や「短冊切り」など生で食べると消化促進効果をより得られます。
ただし、加熱するとでんぷんが糖化して甘みが増し、ホクホク感が楽しめるなど、別の美味しさやエネルギー補給効果が得られます。つまり、生と加熱で栄養の“活かし方”が変わるのです。
Q. 長いもは皮付きのまま調理した方がよいですか?
A. はい、皮のすぐ下にはポリフェノールやミネラルなどの栄養素が豊富に含まれています。そのため、タワシで表面の泥や汚れをしっかり落とせば、皮付きのまま調理するのがおすすめです。
皮ごとすりおろすと粘りが増し、素揚げやステーキにしても香ばしく仕上がります。見た目を重視したい料理やおもてなしの場合はむいてもOKですが、栄養価を考えるなら皮ごとがベストです。
Q. 切るときの方向は?
A. シャキッと食感を楽しむなら繊維を断ち切る横切り、粘りを活かすなら縦切りです。
Q. 髭(ひげ根)はどうしたらいい?
A. 食べても問題ありませんが、ガス火であぶるか包丁で落とすと口当たりが良くなります。
Q. すりおろすとかゆくなるのはなぜ?
A. 針のような形をした「シュウ酸カルシウム」の結晶が皮膚を刺激するためです。酢水で洗う・手袋をするなどで防げます。
Q. 保存方法は?
A. 丸ごとは新聞紙に包み冷暗所、カット後はラップで冷蔵保存を。すりおろしてチャック付きポリ袋に入れて冷凍保存するのも便利です。冷凍しても栄養価は変わりません。
Q. 北海道以外でも長いもは採れるのですか?
A. はい、青森県や長野県などでも栽培されています。ただし、全国の生産量の半分以上を占めるのは北海道で、特に十勝や網走の長いもはブランドとして有名です。
Q. ネバリスターと大正長いも、どちらがおすすめ?
A. 粘りを楽しみたいならネバリスター、シャキッと食感やさっぱり感を重視するなら大正長いもです。
Q. 長いもはなぜおが屑で包まれているのですか?
A. 長いもはとても折れやすく、衝撃や乾燥にも弱い野菜です。そのため、収穫後の輸送時にはおが屑をたっぷり詰めて緩衝材にし、折れや乾燥を防いでいます。おが屑に包まれていることで、鮮度を保ちながら全国に出荷できるのです。
まとめ
北海道産の長いもは「栄養」「粘り」「食感」のバランスが絶妙。
ネバリスターの粘り、大正長いものみずみずしさ、網走産の爽やかな甘み――。どれも食卓に“もう一品欲しい”を叶えてくれる存在です。
今が旬の北海道産長いも。ぜひご家庭で取り寄せて、栄養満点のおいしさを味わってみてください。